「東京のやり方は捨てろ」
柔和な笑顔で飲みに応じてくれた木嶋さんが、本題に入って開口一番に口にした言葉はこれだった。面食らって目をぱちくりさせるおれに、木嶋さんが笑いかける。
「びっくりしたか。お前、おれがこんなこと言うと思ってなかったやろ。本社の誇りを持ち続けてやっていけ。とか、言うと思っとったやろ」
元々関西出身だった木嶋さんの喋りが、ここではよく馴染む。けど、木嶋さんが何を言いたいのか、いまいち見えて来ない。新製品導入で、共に苦労した四年間。あの時の木嶋さんは、こんなことを言う人だったか。転勤して三年。三重色に、染まってしまったんだろうか。
「おれかてな、ホンマはこんなこと言いたくない。東京方式の誇りを持ってやっていきたい。そう思っとるお前の気持ちは、よおわかる。けど、それじゃ、あかんのや」
それじゃあ、ここで生き残っていけへんのや。そう、木嶋さんは断言した。
郷に入れば、郷に従えというのか。それは確かに、一理ある。けど、そんなことをしていては、各企業の成長は臨めないんじゃないのか。
「あんな、お前も薄々気付いてるとは思うが、おれたちはもう本社へ帰属することは無いんや。辞める気が無いんやったら、この地で骨埋めるつもりでやるしかない」
そういう、話か。
漸く、思考が回って来た。確かにおれたちは、下請け会社に指導員として派遣されたような栄転ではない。膨れ上がった人員削減と言う名のリストラを体裁よくやるために並列子会社に流された、左遷組なのだ。
左遷組なのだ。あの、塩谷さえも。
「ここで生き残りたければ、ここのやり方に馴染め。おれが金山に伝えたかったのは、それだけ」
そう言うと、木嶋さんは作という鈴鹿の酒を啜って、おれにも注いだ。
白い、何の変哲もないお猪口を手に取る。底に描かれた青い輪っかがぐるぐると回って、脳裏に回って、焼き付く。
「おれは、何しに三重まで来たんでしょうね。服なんて、たいして好きでもないクセに」
「服なんて、たいして好きじゃない方が長く続く。おまんまの食いっぱぐれが無いように、付いてきたんやろ」
違いない。木嶋さんの言っていることは正しい。確かに、就職活動中の大学生時代、韓国籍でも問題なく雇ってくれそうな大手企業に絞ってエントリーシートを出していたのは間違いない。名前だって、教授に勧められた通りに通名を使って入社した。第一印象で偏見を持たれないための対策だ。でもおれは、入社当時にはもっと何か、夢を持ってここに来たはずだった。アジア産で低価格のファスト・ファッションが主流になるこの日本で、高級色を前面に押し出さない国内産の衣料をどう押し出すか。そういう挑戦に、夢を見出していたはずだった。でも今は、他の大手アパレルメーカーと同じく、中国やバングラデシュに生産工場の委託を展開しだしている。最初に見ていた夢は、もう消えたのだ。
おれの、ここでの存在意義は何だ。ここで、腐らない方法は何だ。塩谷みたいに、得意分野を伸ばせばいいのか。おれの得意分野ってなんだっけ。梅雨アイテム以外の経験や知識って、何か持ってたっけ。
「そういえば今回、塩谷も一緒に来たんやろ。あいつらが新人やった頃、お前よく面倒見てたよなぁ」
「そうでしたっけ」
「そうそう。塩谷にされた質問を調べて、ノートにまとめてさ。毎日遅くまで残ってたやん」
そういえば、そんなこともあった気がする。でもそれは、後輩に聞かれて判らない自分が悔しかっただけだ。
「自覚ないんかも知らんけど、金山はけっこう面倒見のええとこあるで。塩谷たち後輩に限らず、派遣さんの契約更新書類やって、いっつもお前が配ってたやん。あんなん、業務課の仕事やのに」
「それは、業務の人員がバカみたいにころころ異動して、申し送りが追いついてないから」
「そういうとこが、面倒見ええって言ってるねん」
まぁ飲めや。今日は、とことん。木嶋さんはおれの反論を遮って、またとっくりを傾ける。お猪口の底の青が、ぐるぐる回る。ぐるぐる回って、空っぽになった。酒も、思考も、こころも、ぜんぶ。
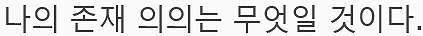
メモ帳代わりにしている付箋紙の一番上にそう書いて、デスクトップの左サイドに貼り付けた。息を吐く。それが溜め息みたいに聞こえて、慌ててもう一度深く息を吸い込む。これなら、深呼吸に見えなくもない。
いや、こんなこと気にしている方が滑稽だ。誰がおれの行動なんて見ているというのだ。逐一チェックしている人間なんて、居るはずもない。第一、いま課長は定例会議で席を外している。
そう思ったが、やっぱり視線を感じて振り返ってみた。
「あ、」
目が合った。彼女が声を上げる。ホントに見られていた。おれは声も出せずに固まる。
社員割りで買ったであろう、自社の低価格ラインであるコーラルピンクのカラーパンツに、無地のTシャツといったラフな格好をした女性がドア付近に立っている。首に下げているのは、メジャーと社員証のネックストラップ。生産課の社員か。
「あの。大変、ですね」
何のことを言っているんだろう。と思ったが、どうも様子がおかしい。視線が合ったのは一瞬で、彼女はおれじゃなくて別の物を見詰めている。その視線の先にあるのは、おれの背後。
もしかして。
「読みました、これ」
「え。あ、読んでませんよ。字が、お綺麗だなーって、思って」
つまり、見てたんですよね。文字を。
詰問調で言ってしまった所為か、すぐに彼女はこの場を去ってしまった。おれは慌てて、パソコンのモニター画面の縁にべたべたと貼り付けた付箋紙を読み返す。パソコンの起動ⅠDに、品質管理ソフトのパスワードに、本日のトゥ・ドゥ・リストに、ハングルで書かれたイデオロギーな言葉がふたつ。
あの人、たぶんこのハングルを読んだんだろう。
こないだの、イライラをぶちまけただけの罵詈雑言を見られなかったことは不幸中の幸いだが、これはこれで問題があるように思う。パソコンの目の前に貼り付けた言葉が、おれの存在意義はなんだろう。これじゃまるで、病んでる人間みたいだ。
それにしても。あの女性は、なんでハングルが読めたんだろう。もしかして、同族なんだろうか。それとも一昔前に流行った韓流ドラマのファンで、勉強したクチだろうか。いや、それにしては年が若い気がする。よく見えなかったが、俺よりは確実に二、三は下だ。その年代にも需要はあるだろうか。じゃあやっぱり、おれと同じで在日の人間なんだろうか。
どっちであっても、そのどれでもなくても、気になる。
生産課の人間がわざわざこのフロアに来たということは、誰かに用事があって来ているはずだ。接触した人に聞けば、彼女がどういう人物なのか、判るかもしれない。
「あの。さっきここに来ていた、ピンクのカラーパンツ履いてた女の子のこと、教えてもらえませんか」
「えぇっ」
業務課で一番年配の高橋さんに直球で質問したら、目を丸くされた。何か、おかしなことを言っただろうか。
「ジョンくん、ロコちゃんみたいな子がタイプなの」
は。何の話をしている。
「ジョンさんとロコちゃんかぁ。なんか、釣り合わへんなぁ。年上がええんやったら、もっと美人な独身の子、カスタマーセンターにいっぱいおるで」
話が噛みあわない。高橋さんに聞いたはずなのに、隣の関根さんが横槍を入れる。
「いや、美人とか年上とかどうでもいいんで。彼女のことが知りたいんです。ロコさんって言うんですか。生産課の人ですよね」
「まぁ、生産課の子やけど。勝手に個人情報は教えられへんなぁ。コンプライアンス違反になったら、厄介やからなぁ」
厄介なのはお前らだろ。何でイチ社員の名前と所属を知るのに、こんな阻まれなきゃならない。
「あ、もういいです。自分で何とかするんで」
面倒臭くなって事務所を飛び出した。現場に行けば、見つかるかもしれない。
「ジョンさん、頑張って。私、応援してますッ」
背後で、何故か新人の原さんが黄色い声援を送ってくる。一体何なんだ、ここの人たちは。
|