BACK ◆HOME◆ NEXT
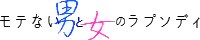 ネット小説ランキング
に投票 | ←面白かったらクリックお願いします♪ | 感想などくださる方はHOMEへ(^-^) ネット小説ランキング
に投票 | ←面白かったらクリックお願いします♪ | 感想などくださる方はHOMEへ(^-^)
【作者のこぼれ話】 2012/04/03/Tue
自称・オトメ小説第二話。職場のマドンナ・アラシフミさん登場。私の職場にも派遣事務員の長身ですらりとした女性がいます。
女の人から見ればステキな彼女も、微妙に身長にコンプレックスのある岩原くんから見れば小さい女性のほうが気に入ったりして。
不美人も三日経てば愛嬌に変わるのか?それもホントウのことみたいですよ。以前、職場で女の子の話題で盛り上がっていた男性陣の会話を盗み(?)聞きした際に知った事実。(一部の男性だけかも知れませんが・・・)三日は嘘にしても、一年前はイマイチ評価だったはずの女の子が、性格と笑顔が判った一年後には何故か陰のアイドル扱いまで昇格していたもんで、驚きです。男の子たちからそんな話を聞いた日にゃ、希望が持てますね(←激しく勘違い!笑)
ってか今更だけど、1話の風俗嬢といい、このタイトルといい、「昭和臭さ」が漂っていると感じるのは私だけでしょうか?
(C)2014 SAWAMURA YOHKO
|