BACK ◆HOME◆ NEXT
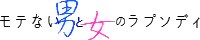 ネット小説ランキング
に投票 | ←面白かったらクリックお願いします♪ | 感想などくださる方はHOMEへ(^-^) ネット小説ランキング
に投票 | ←面白かったらクリックお願いします♪ | 感想などくださる方はHOMEへ(^-^)
【作者のこぼれ話】 2012/03/30/Fri
ちょっとイロイロ触発されて、久々に物語を書きたくなりました。
最近、「大人の女性のための少女まんが」ってやつにはまってまして。
そういった雰囲気のある青年漫画(主に恋愛モノ)をBOOK
OFFでまとめ買いしてよく読みます。だからそんな雰囲気を目指したつもり。
物語と主人公のモデルは学生時代にアルバイトをしていたコンビニの仲間たちとその常連客のおねえさん。そして今の職場と自分自身。
職場のアイドルには程遠い、間違ってもかわいいとは形容できない女性がヒロインとして登場する、アラサー女の恋愛事情。
女性の職場にいないため、オンナゴコロが判らなさ過ぎて女性を主役には据えられませんでしたが、これは「オトメ小説」です!(断言)
(C)2014 SAWAMURA YOHKO
|